当連合会では、産業廃棄物の処理に携わる方々に対し、産廃処理の基礎的な知識の習得を目的とした研修会、産業廃棄物処理業を営むために必要とされる安全な処理に関する知識や技術の向上に関する研修会、スキルアップを目指す方の検定試験など、人材育成を目的にした様々なプログラムを開催しています。また、厚生労働省では、産業廃棄物処理業「職業能力評価基準」を策定しています。
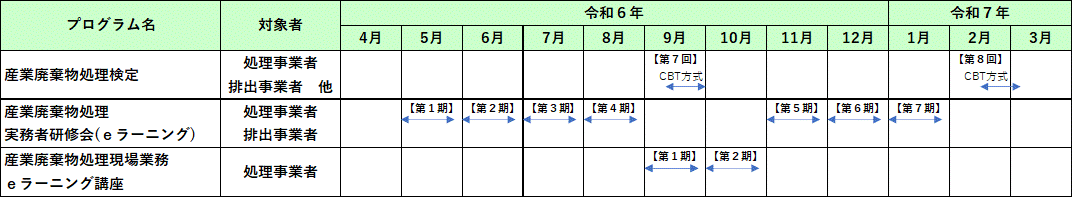
厚生労働省では、「職業能力が適正に評価される社会基盤づくり」として、能力評価のいわば“ものさし”、“共通言語”となる職業能力評価基準の整備を進めています。
この基準は、求職者・労働者にとっては、①自らの能力の客観的な把握、②企業が必要とする能力の把握が可能となり、職業能力の向上に向けた取組につなげることができます。また、企業にとっては、採用すべき人材の明確化、人材育成への効果的な投資、能力に基づいた人事評価・処遇等の導入・定着に関するスタンダードとして活用することができます。
産業廃棄物処理業についても、業界の実態を踏まえた職業能力評価基準が作成されていますので、従業員に対する能力開発やキャリア形成支援の指針として、また、求人時の能力の明確化等、様々なニーズに応じて活用することが可能です。